NPO・NGOインターンシップ
Vol.10 「知る楽しさを伝えたい」 ─理科教師を志す大学生がインターンで見つけた本当の学び
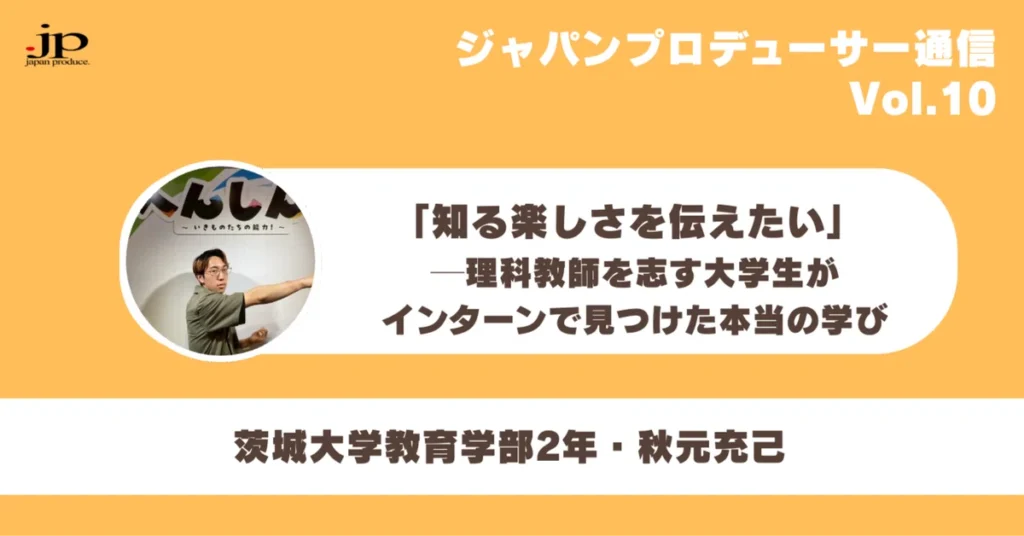
── あなたは、宿題にどんな思い出がありますか?
終わらせるのが目的だった、という人も多いかもしれません。けれど、「学ぶって、本当は楽しいことなんです」と語る大学生がいます。
教育学部で理科の教員を目指す秋元充己さんは、インターンシップを通して、子どもと向き合う意味を見つめ直しました。
彼はまさしくインターンシップという環境を最大限使い倒したと言っても過言ではありません!
今回はそんな彼にお話を聞いてみました!
◎プロフィール
・名前:秋元充己
・大学:茨城大学教育学部理科専修2年
・年齢:19歳
・出身:福島県
→大学1年生の春休みにインターンシップに参加
▶︎「好奇心」と「行動力」で突き進んだ、秋元さんの原点
茨城大学教育学部で学びながら、子どもたちと向き合う教育の道を志している秋元充己さん。彼の原点には、「好奇心旺盛で活発な子どもだった」という幼少期の姿があります。
そんな彼に転機をもたらしたのは、小学生の頃に見たテレビ番組「仮面ライダーオーズ」。
番組の中で主人公が放った「手を伸ばさなきゃ後悔する」という言葉に胸を打たれた秋元さんは、体操クラブへの入会を決意しました。

小学校5年生から本格的に体操を始め、選手コースに進んだ彼は、数々の大会で輝かしい成績を収めていきます。
中学生のときには福島県いわき市大会で優勝。
さらに高校では3年連続でインターハイ出場するという快挙を達成しました。
彼の名前は学校の門に掲げられ、名実ともに「トップ選手」の仲間入りを果たしました。
現在でも大学の体操部に所属し競技を続ける一方、教育実践サークルにも所属。
教師に必要なスキルを身につけるため、模擬授業や音読指導などに取り組んでいます。
特に、指導に必要な人前で話す力や、聞き手を巻き込む力を養ってきました。「笑顔・目線・声」「不要な言葉をなくす」など、日々の実践を通して意識してきたポイントが、確かな成長につながっています。
▶︎ “理論”と“現場”のギャップに気づいたインターンシップ体験
秋元さんが、ドットジェイピーのインターンシップに参加したのは、友人からの紹介がきっかけでした。
母校での卒業生講演で再会した友人から、「学校以外で子どもと関わる貴重な経験ができる」と聞き、迷わず参加を決めたといいます。

実際にNPOインターンシップを始めてみると、子どもたちの姿にすぐに魅了された秋元さん。
「とにかく可愛い」と笑顔で語る彼ですが、ただ楽しむだけではありませんでした。
大学で研究していた「認知の理論(=人が物体をみた時に、どのような使い方をするのかという心理学)」を踏まえ、子どもたちの行動を観察。
理論通りに動く子どもは実際にはおらず、自分なりに仮説を立て、現場でそれを検証するという学びの姿勢が生まれたといいます。
たとえば「子どもは座ったとき、どんな行動をとるのか」といった些細な観察も、秋元さんにとっては貴重な検証の場。
こうした積み重ねを通して、「大学の学びは抽象的だからこそ、現場では子ども一人ひとりに向き合うことが大切だ」という価値観を獲得しました。
さらに、インターンを通じて身についたのが“絵本の読み聞かせ”のスキルです。
子どもの注意を引き、感情に訴える語り口を磨くことで、教育者としての表現力にも磨きがかかりました。
▶︎「宿題は楽しいもの」── 子どもに寄り添った教え方で見えた未来
インターン活動のなかで、秋元さんにとって特に印象的だったエピソードがあります。
それは、最終日の授業で小数点の繰り上がり・繰り下がりについて教えたときのこと。
「子どもが『わかりやすい!』と感動してくれたんです」と語る彼の目は、今でもそのときの嬉しさを映していました。
秋元さんには、もともと「宿題とは、終わらせることが目的ではなく、学びの楽しさを知るためのものだ」という教育観があります。
その考えをもとに宿題の問題の解き方を教えた結果、子どもが楽しそうに解く姿を見ることができたことが、何よりの喜びでした。
「宿題の本来の意義を、指導者自身が一番理解しておく必要がある」。
そう断言する秋元さんの姿からは、教育に対する真摯な姿勢と情熱が伝わってきます。
▶︎理科の先生として「知る楽しさ」を伝えていく
今後のビジョンを尋ねると、秋元さんは迷いなく答えてくれました。
「理科の先生になりたい。そして、子どもたちにとって“人間としての手本”となる存在でいたい」と。

大学生活では引き続き「認知の理論(=人が物体をみた時に、どのような使い方をするのかという心理学)」の研究を深め、「理科教室の設計が生徒の集中力にどう影響するのか」というテーマに取り組む予定です。
また、秋元さんが社会に伝えたいメッセージとして語ってくれたのが「知る楽しさ」でした。
「人は、誰かとの会話のなかで気づきを得る。その気づきが、好き嫌いの芽生えにつながる。だからこそ、人生を豊かにするには、知識や考え方を増やした方がいい」。
学びとは、単なる受験や資格のためではなく、自分の人生を豊かにする“手段”なのだと、彼は力強く語ります。
この想いは、既に母校での卒業生講演でも語ってきました。
そして将来、理科の先生になってからも語り続けていく彼の信条です。
「今の大学生活で何か物足りなさを感じている人は、ぜひインターンに挑戦してほしい。大学の中でやり切った人ほど、新しい場所で大きく成長できる」。
そう語る秋元さんの姿に、未来の教育者としての覚悟と優しさがにじんでいました。




